子どもに「もっと本を読んでほしい」「本好きに育ってほしい」と思いながらも、なかなか読書習慣が身につかない…そんな悩みを抱えているパパ・ママは少なくありません。
この記事では、私自身の体験も交えながら、子どもが自然と読書好きになるための習慣の作り方や、年齢別のアプローチをご紹介します。
なぜ今、読書習慣が大切なのか?
読解力・集中力・語彙力が育つ
読書は単なる趣味ではなく、子どもの思考や語彙力を育てる最高の習慣です。文部科学省の調査でも「日常的に本を読む子どもほど、学力や思考力が高い傾向にある」とされています。
デジタル社会でも「紙の本」の価値は高い
スマホやタブレットに触れる機会が増えているからこそ「紙の本に集中する時間」が貴重になっています。目を休める効果もあり、情報に流されない力が自然と身につきます。
読書習慣がつかない子に共通する3つの原因
本を読む「楽しさ」を知らない
読書がつまらない・難しいものだと思っている子は多いです。まずは「本って面白い!」と思える体験をさせてあげることが第一歩。
テレビ・YouTube・ゲームが優先になっている
我が家でもそうでしたが、手軽で刺激の強い娯楽があると、読書は後回しになりがち。環境の見直しが重要です。
親自身が本を読んでいない
子どもは親の姿をよく見ています。親がスマホばかりで本を読まない家庭では、子どもも本に興味を持ちづらい傾向があります。
子どもが自然と本好きになる7つの工夫
興味に合った絵本・児童書を選ぶ
「年齢別のおすすめ本」も参考になりますが、まずは子どもが興味のあるテーマ(乗り物、動物、恐竜など)を選ぶのがコツです。
おすすめ:毎月プロが選んだ絵本が届く【絵本ナビ定期便】なども、選書の手間が省けて◎
毎日決まった時間に読書タイム
「朝ごはんのあと5分」「寝る前の10分」など、生活リズムに組み込むことで習慣化しやすくなります。
親子で読み聞かせを習慣に
0~6歳頃までは、「読み聞かせ」こそ最高の知育。音やリズム、親の声で本の楽しさを知ることができます。
子供の目線に合わせた本棚を作る
表紙が見えるように並べる「前向き収納」は、子どもが自分で本を選びやすくなる工夫です。
図書館や本屋に定期的に行く
無料で使える図書館は、読書習慣のきっかけ作りにぴったり。お気に入りの一冊に出会うチャンスです。
親が読書している姿を見せる
子供に「読んで」と言うよりも、親が自然に本を読んでいる様子を見せることのほうが効果的です。
読書記録やごほうびシールで楽しく
我が家では「読んだ本を記録する読書ノート」と「スタンプカード」で、やる気UPに成功しました。
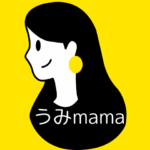
読書ノートにパパママからのコメントを書いたり、ごほうびシールを貼ったり!親子のコミュニケーションツールにも◎
年齢別|読書習慣の作り方
幼児期(0~3歳)
音や絵のインパクトが強い赤ちゃん絵本や布絵本がおすすめ。スキンシップを重視しながら、親の声で安心感を育てましょう。
幼児後期(4~6歳)
ストーリー性のある物語に興味が出てくる時期。読み聞かせから”「一緒に読む」→「自分で読む」への移行”を目指します。
小学生(7歳~)
一人読みが進む時期。選書に口を出しすぎず、マンガや図鑑も読書の一部として肯定するのがポイントです。
読書習慣がうまくいかなかったときの対処法
無理に読ませない
「読書しなさい!」は逆効果。興味が持てるようなしかけやきっかけ作りにフォーカスしましょう。
本のジャンルを変えてみる
ストーリーよりも、図鑑・間違い探し・なぞなぞなど「読み物以外の本」が好みに合うこともあります。
読書=静かに1人で読む…とは限らない
音読したり、マンガを通じて言葉に親しむことも立派な読書体験です。
私が実践した読書習慣づくりの体験談
朝5分の読み聞かせを始めてから
保育園の準備でバタバタしていた朝ですが、5分だけでも読み聞かせタイムを取り入れると、その日一日落ち着いて過ごせるようになりました。
図鑑からハマって、物語好きに成長
最初は「のりもの図鑑」ばかり読んでいた息子が、ある日から関連する物語にも手を伸ばすように。「好き」から広げる読書の力を感じた瞬間でした。
よくある質問(Q&A)
Q.読書が嫌いな子どもに、どう接すればいい?
→本に触れるきっかけがあれば十分!マンガや図鑑でもOKです。
Q.何歳から読書習慣は始めるべき?
→読み聞かせは0歳からスタート可能。習慣化は早ければ早いほど◎です。
Q.スマホばかり見ている場合の対策は?
→タブレットの読み聞かせアプリ(例:ピッケのつくるえほん)など、読書に寄せる工夫もおすすめです。
まとめ|焦らず、比べず、楽しくが大切!
読書習慣は、「読まなきゃ」ではなく「読めたらうれしい」から育てていくもの。
子どもが本の世界を好きになれるよう、家庭に”本がある風景”を少しずつ増やしていくことが、一番の近道です。






コメント