2歳の寝かしつけ、どうしてこんなに大変なの?
「もう夜の寝かしつけが苦痛…」そんなふうに感じていませんか?
2歳はちょうどイヤイヤ期に突入する時期。自我が強くなり、何に対しても「イヤ!」と主張するようになります。そしてその影響は、夜の寝かしつけにも大きく現れます。
- ベッドに入らない
- 何度も起きる
- 泣く、暴れる
- お布団を蹴飛ばす…
SNSでも、「2歳 寝ない」「2歳 寝かしつけ 疲れた」という悩みが毎日のように投稿されています。
この記事では、2歳児の寝かしつけがうまくいかない理由と、すぐに実践できる5つのコツを紹介します。私自身、2歳児の育児を通して実践してきた方法なので、ぜひ参考にしてください。
なぜ2歳の子どもは寝ないのか?その理由
1,自我の成長と「イヤ!」が増える時期
2歳は「自分」という意識が強まり、すべてに自分の意志を反映させたがります。
「まだ遊びたい」「ママといたい」「寝たくない」―――このような気持ちが、寝る時間になると爆発するのです。
2,昼寝や活動量による生活リズムの乱れ
昼寝が長すぎたり、日中の運動量が少なかったりすると、体が疲れておらず寝つきにくくなります。昼寝が夕方までずれ込むと、夜寝るのが遅くなる悪循環に。
3,好奇心旺盛で寝るのがもったいない
「もっと絵本を読みたい」「もっと遊びたい」―――2歳児は脳も活発に働き、どんどん吸収する時期。そのため、「寝る=楽しい時間が終わる」と感じ、拒否反応が出ることも。
4,不安や寂しさから来る夜のぐずり
昼間の出来事をうまく処理できず、不安や甘えが強く出ることがあります。特にママとの関係が深いほど、「一緒にいてほしい」と感じて寝かしつけに時間がかかる傾向があります。
2歳の寝かしつけ、試してほしい5つのコツ
1,就寝前のルーティンを固定する
寝る前の流れを毎日同じにすることで、「そろそろ寝る時間だ」と子ども自身が認識できるようになります。
例:夕食→お風呂→絵本→トントン→就寝
この順番を崩さないことが大切です。
2,テレビやスマホは寝る1時間前まで
ブルーライトは脳を覚醒させ、眠気を妨げます。
就寝時間1時間前はテレビやスマホを切り、落ち着いた環境を整えましょう。代わりに、音楽や絵本で静かな時間を過ごすのがおすすめです。
3,昼間にたくさん体を動かす
日中にしっかり体を動かすことで、夜にぐっすり眠りやすくなります。
公園や散歩、室内でもジャンプ遊びなどで体力を消耗させましょう。
4,子どもに「選ばせる」関わり方
2歳児は「自分で決めたい」という気持ちが強いため、「パジャマどっちにする?」「どの絵本読む?」など、選択肢を与えると納得しやすくなります。寝かしつけもスムーズに進みやすくなります。
5,寝かしつけにイライラしない工夫(親のメンタル)
親がイライラすると、子どもも敏感に察知して余計に寝なくなります。
お気に入りの音楽を流す、深呼吸をする、アロマを使うなど、自分の心を落ち着ける工夫も大切です。
やってはいけない寝かしつけNG行動
寝る直前に叱る/怒る
不安や恐怖で眠れなくなり、悪循環に。
暗い部屋でスマホを見せる
光が脳を刺激し、眠気を遠ざけてしまいます。
日によって寝る時間がバラバラ
リズムが乱れ、寝かしつけが難しくなります。
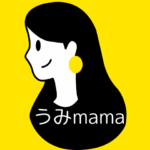
とはいえ、現実は難しいですよね…。
2歳の寝かしつけにおすすめのアイテム5選
育児のプロや先輩ママの間で評判の良い寝かしつけアイテムをご紹介します。
プロジェクター付きおやすみライト
天井に星空を映してリラックス空間に
おやすみ絵本
心を落ち着けるリズムと言葉
子ども用アロマスプレー
ラベンダーなどの香りで安心感をUP
快眠パジャマ
肌触りで寝つきが変わる!
お気に入りのぬいぐるみ
「一緒に寝るお友だち」がいると安心
よくある質問(Q&A)
Q.2歳児の寝かしつけ、何分かかるのが普通?
A.平均で30~60分かかる子が多いです。個人差が大きいため、「うちの子だけ?」と悩まないでOK。
Q.昼寝の時間はどう調整すればいい?
A.13時~15時の間に30~90分が理想です。夕方以降の昼寝は避けましょう。
Q.どうしても寝かしつけが辛いときは?
A.一人で抱えず、家族や育児支援サービスに相談を。「子どもが寝る=親の休息」なので、無理は禁物です。
まとめ|「寝かせる」のではなく「安心させる」がポイント
2歳の寝かしつけは、親にとっても精神力を試される時間です。
でも、子どもにとっては「パパとママと過ごす大切な時間」。
寝かしつけは、ただ眠らせるのではなく、「安心させる」こと。
ルーティン・環境・声かけ・アイテムなど、あなたのお子さんに合った方法を見つけながら、少しずつ「おやすみ」の時間を心地よくしていきましょう。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a643ece.7da3b80b.4a643ecf.fae49aa4/?me_id=1397192&item_id=10000020&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_gold%2Fomoryutsucenter%2Fplanetakari%2F11%2Fprasam11.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a644060.fbdbb6c2.4a644061.231d43c6/?me_id=1213310&item_id=10139010&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0321%2F03217020.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a644311.ea189a0e.4a644312.17d651d1/?me_id=1254266&item_id=10001108&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Faromaspray%2Fcabinet%2Fitem%2Fsp-stress-set_02.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a64458c.14586b42.4a64458d.358e46fb/?me_id=1259988&item_id=10001075&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fllic%2Fcabinet%2Fitem3%2Ftoro-pajama-1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a644854.8f808ad9.4a644855.a7eeeebd/?me_id=1370893&item_id=10000101&pc=https%3A%2F%2Fimage.rakuten.co.jp%2Fmycket-pocket%2Fcabinet%2Fbrand%2Ftinyspoon%2Ftin-006_7.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)



コメント